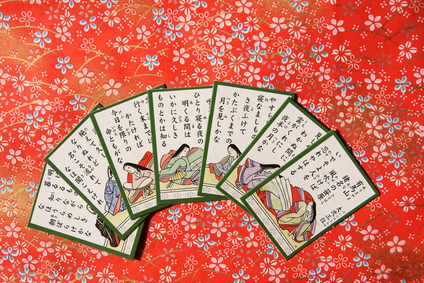
先週末に鹿児島の短歌結社「華」主催の文化講演会があり行ってきました。同結社の発行している短歌季刊誌「華」の100号発行を記念しての講演会です。講師は伊藤一彦氏、岡野弘彦氏でお二人とも中央歌壇で活躍されている方々です。
伊藤一彦氏は演題が「現代と短歌」、副題に「現代を生きるいのちの歌」という内容のお話でした。レジュメに22首もの短歌を用意されて、その全てに鑑賞、解説をされました。その中で気になった歌を抜き出してみます。
不可思議は天に二日のあるよりもわが体に鳴る三つの心臓(与謝野晶子)
与謝野晶子が双子を身籠った時の歌だそうです。だから三つの心臓が体内にあると詠んでいるのですね。男には詠めない歌です。
鷲に吊られ野鼠がは初めて見たるもの己が棲む野の全景なりし(斎藤史)
死を目前にしないと自分の生き様は俯瞰できないのかもしれませんね。野鼠は吊られて全景を見ることができましたが、私は自分の生き様を俯瞰できるかどうかも怪しい限りです。
怒りすらかなしみに似て口ごもる この国びとの 性を愛しまむ(岡野 弘彦)
伊藤氏はこの歌から哲学の話をされました。西洋文化(哲学)は分ける文化で、日本は分けない文化だと。西洋では神と人間を、自然と人間を、そして人間(自分)と人間(他人)を分けて考える。対して日本ではそれらを分けずに合わせようとする。
一神教と多神教の違いなどを思いました。日本には神話の神々はもとより、山や石、空、海、いたる所に神がやどり、人も神となります。権現さまなどは仏様が神様です。融合というか和というか、みんなで一緒にという感じです。
命をテーマにした選歌と公演は、短歌はもとより、短歌を離れても考えさせられる内容でした。
岡野氏は「短歌が一番輝いた時代」という演題で、中世の和歌を中心にお話頂きました。中世では文学(和歌、物語)の世界では、圧倒的に女性の方が優位だったということで、大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)の和歌などをお話くださいました。
来むと言ふも来ぬ時あるを来こじと言ふを来むとは待たじ来じと言ふものを(大伴坂上郎女)
岡野氏はリズムが力を無くしたと嘆いておられました。残念ながら時間が少なくなり詳しく聴けなかったことが残念です。
いつも興味深い講師を招く「華」短歌会です。今回も面白い講演でした。100号というと結社として25周年にあたります。今後の発展を見守りつつ、来年の講演会を楽しみにしたいと思います。